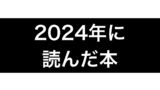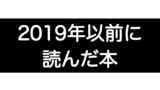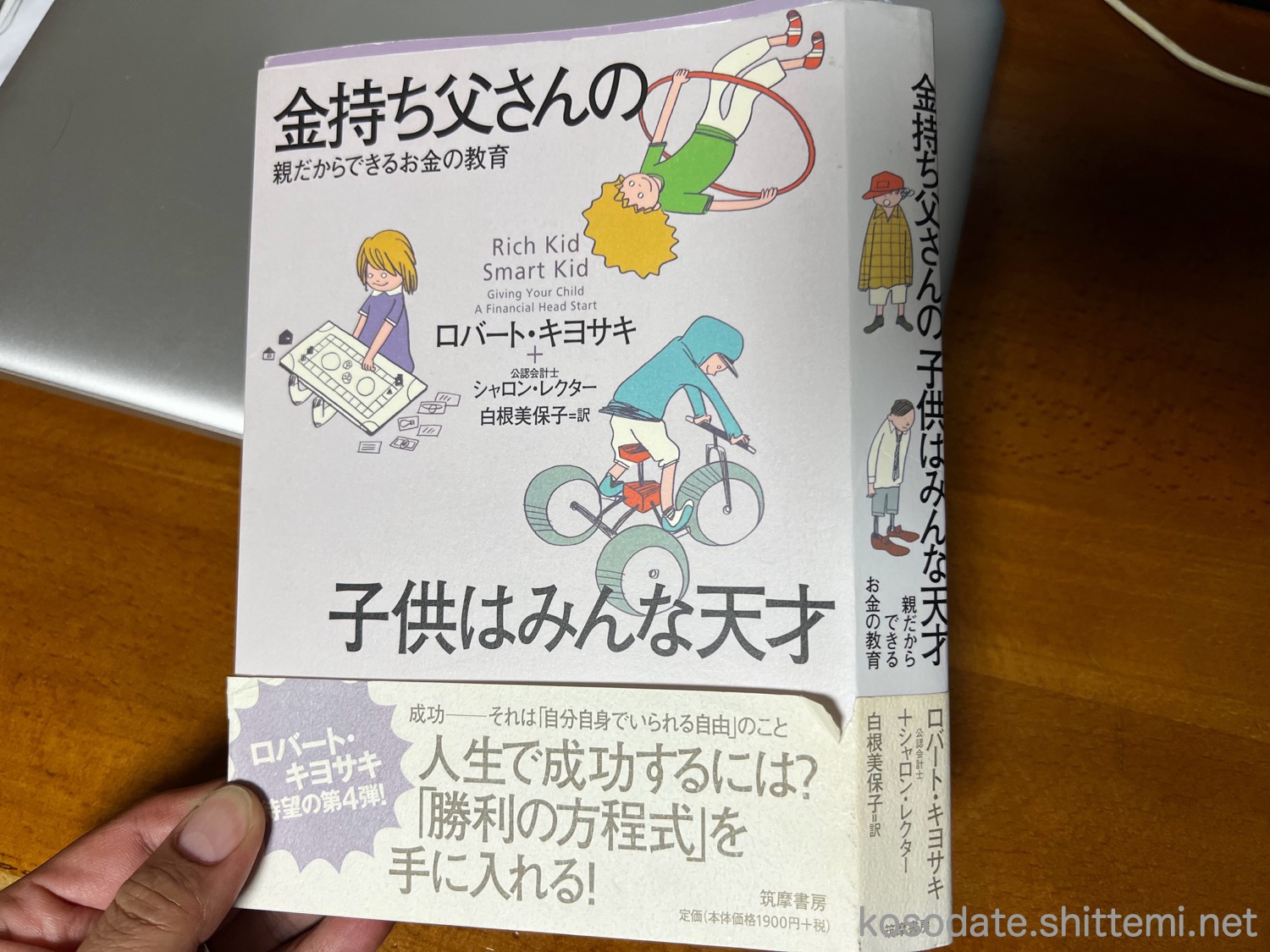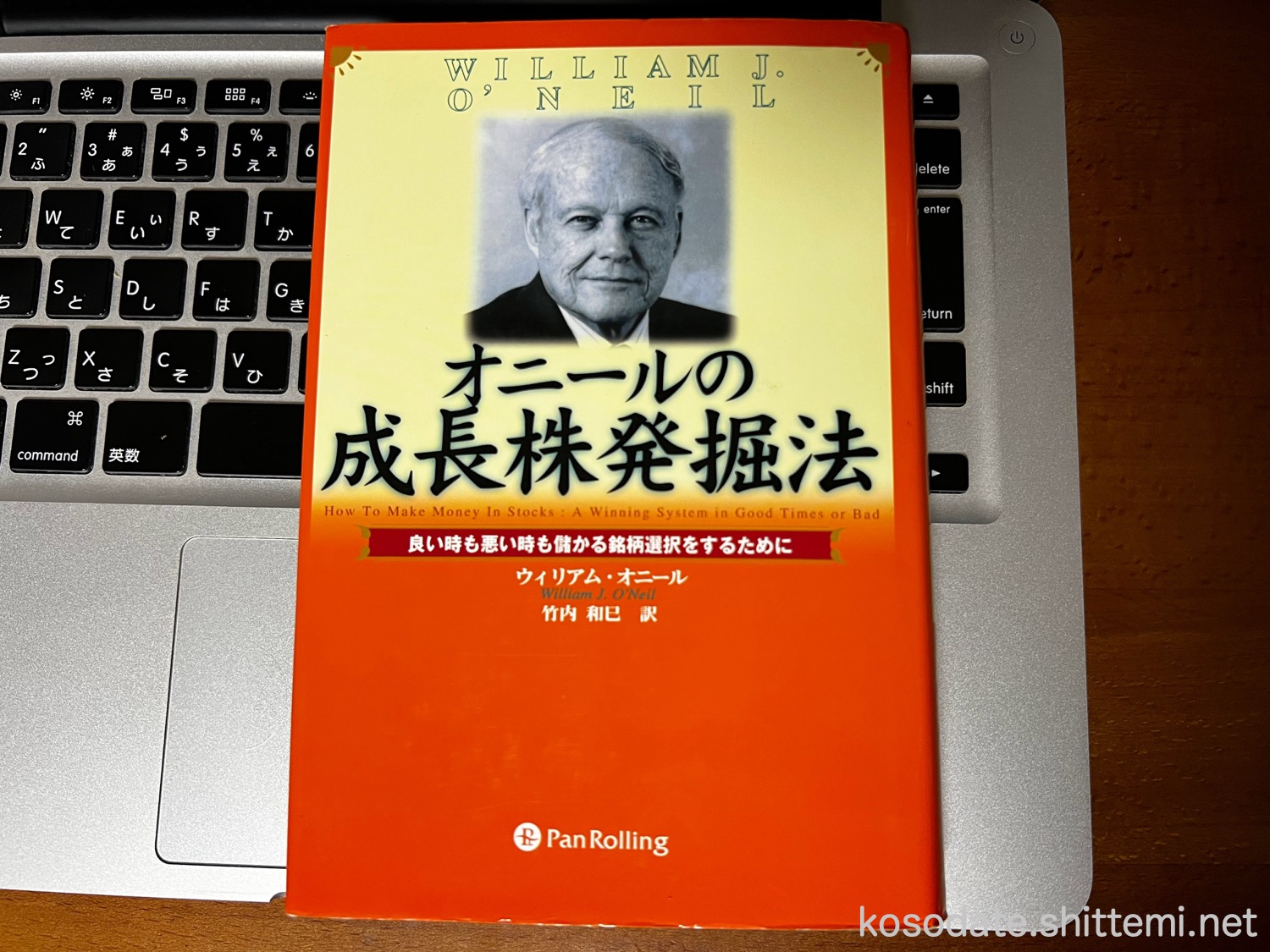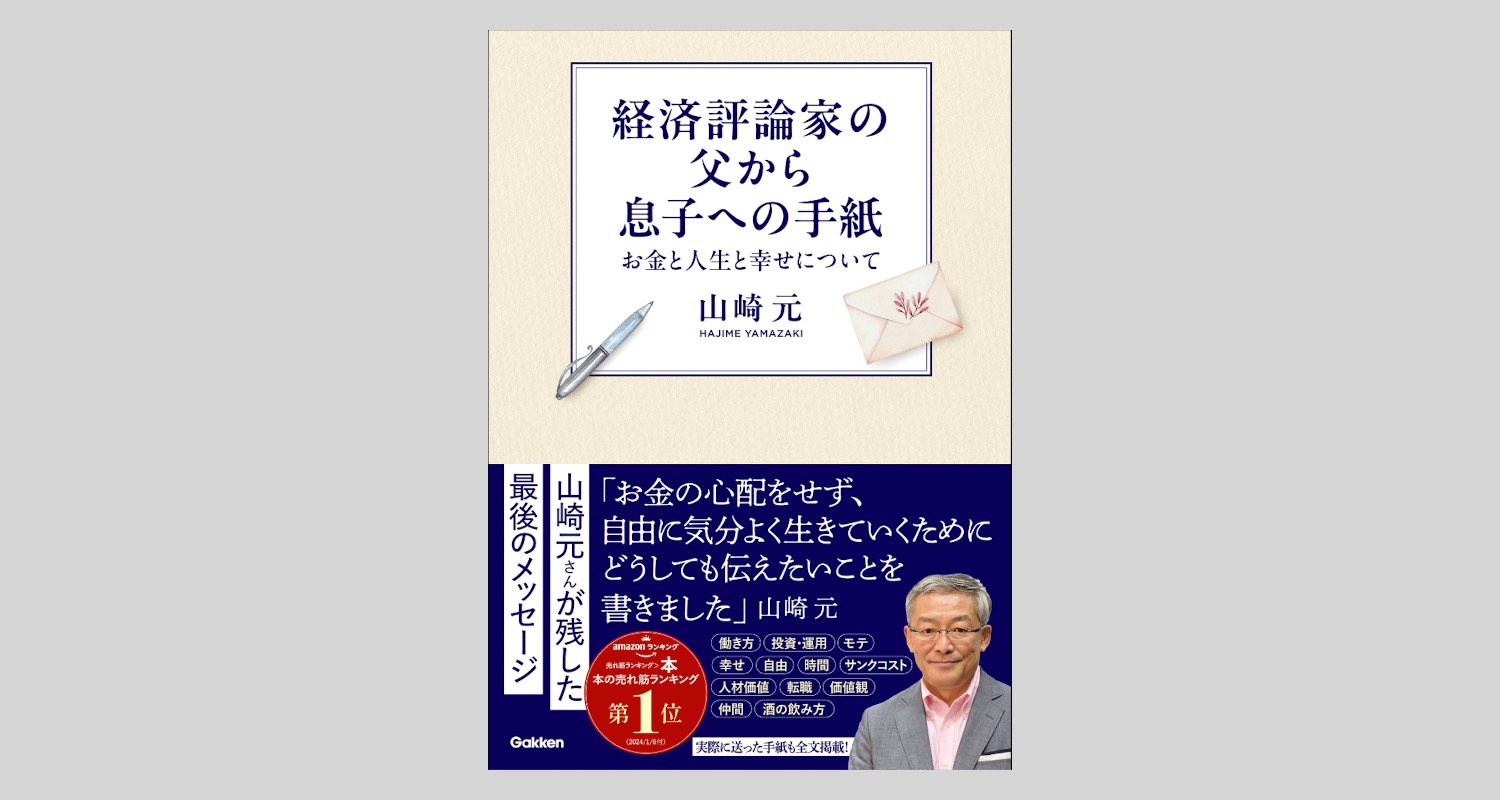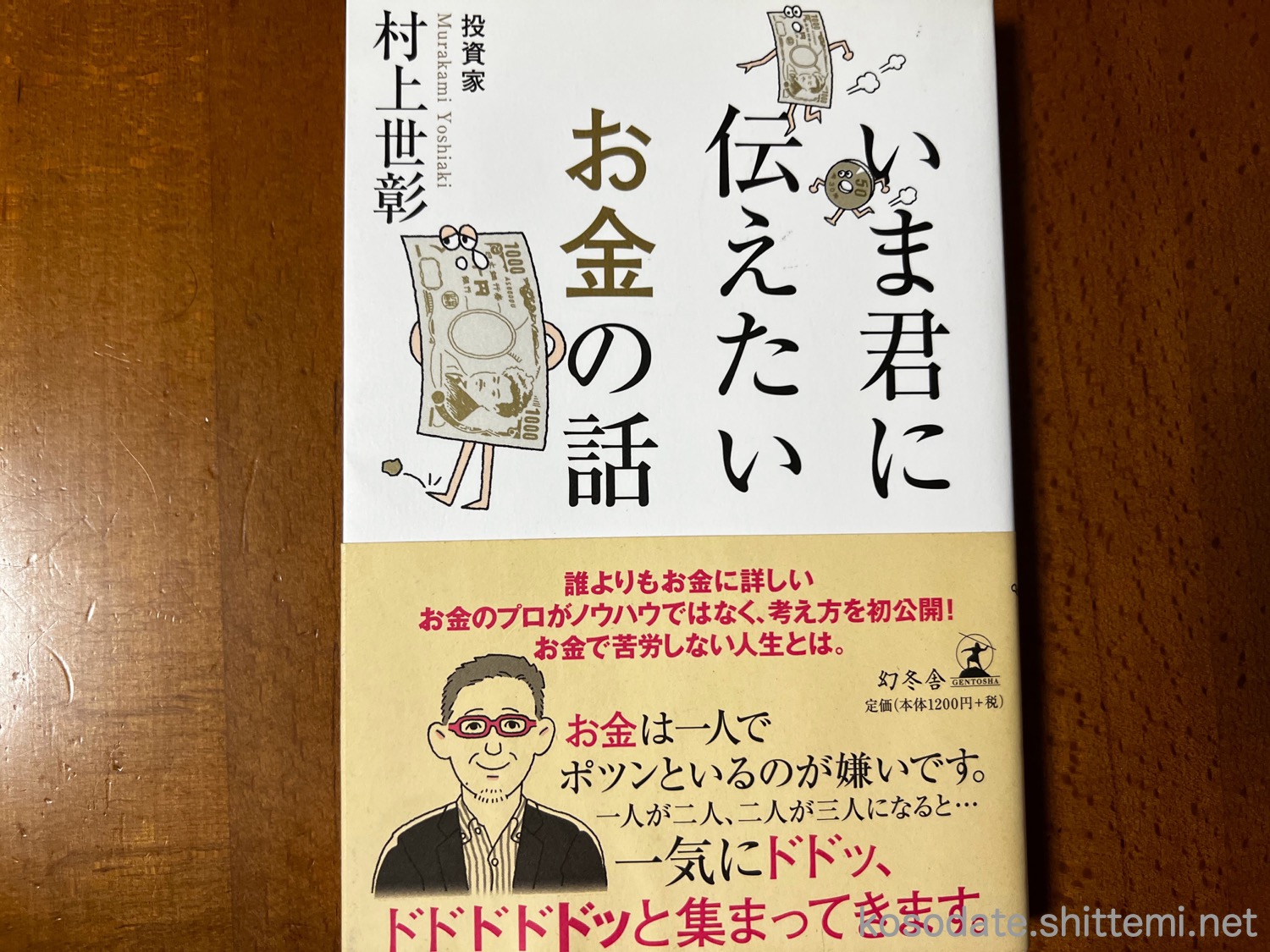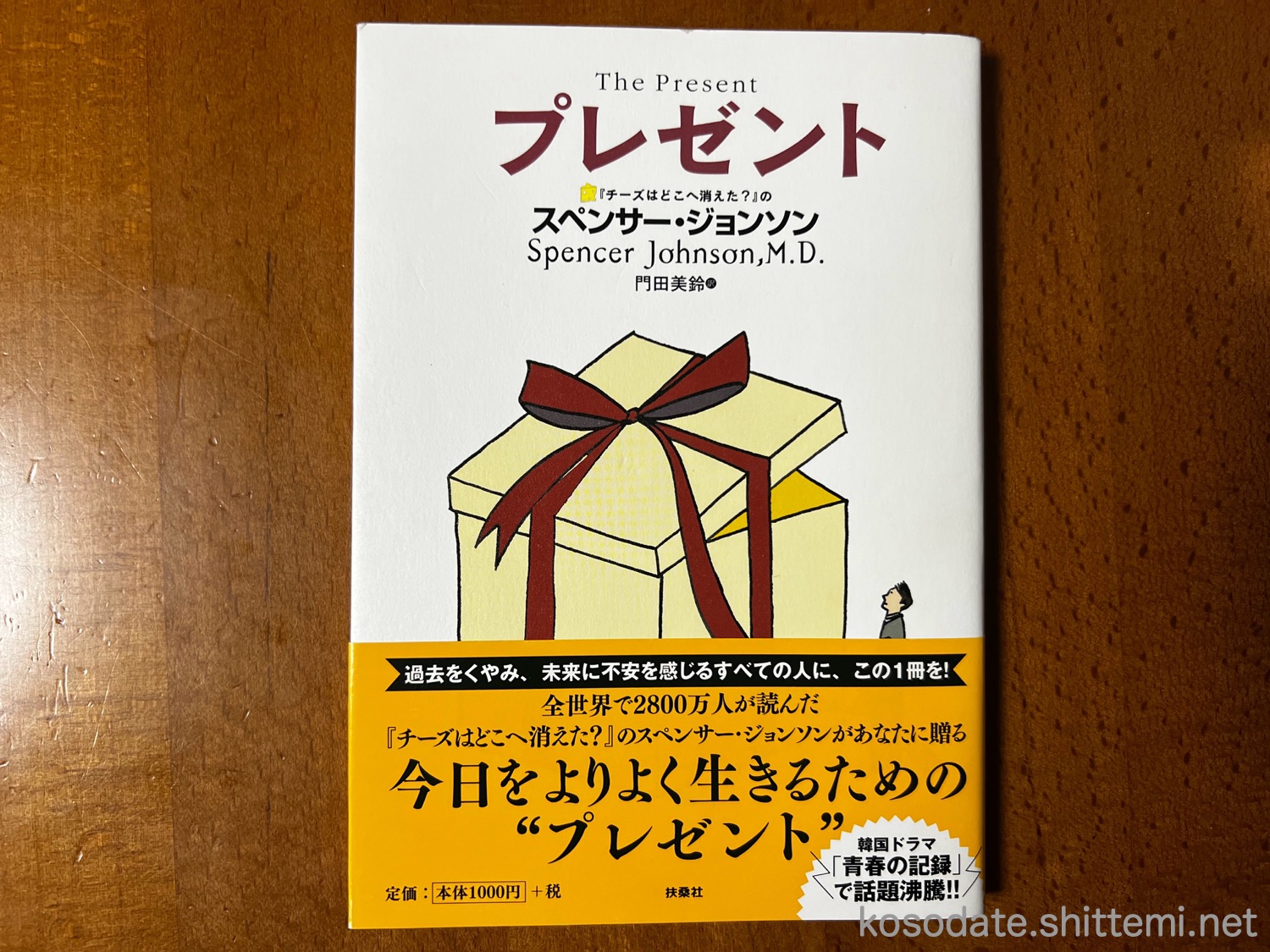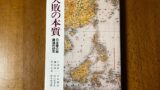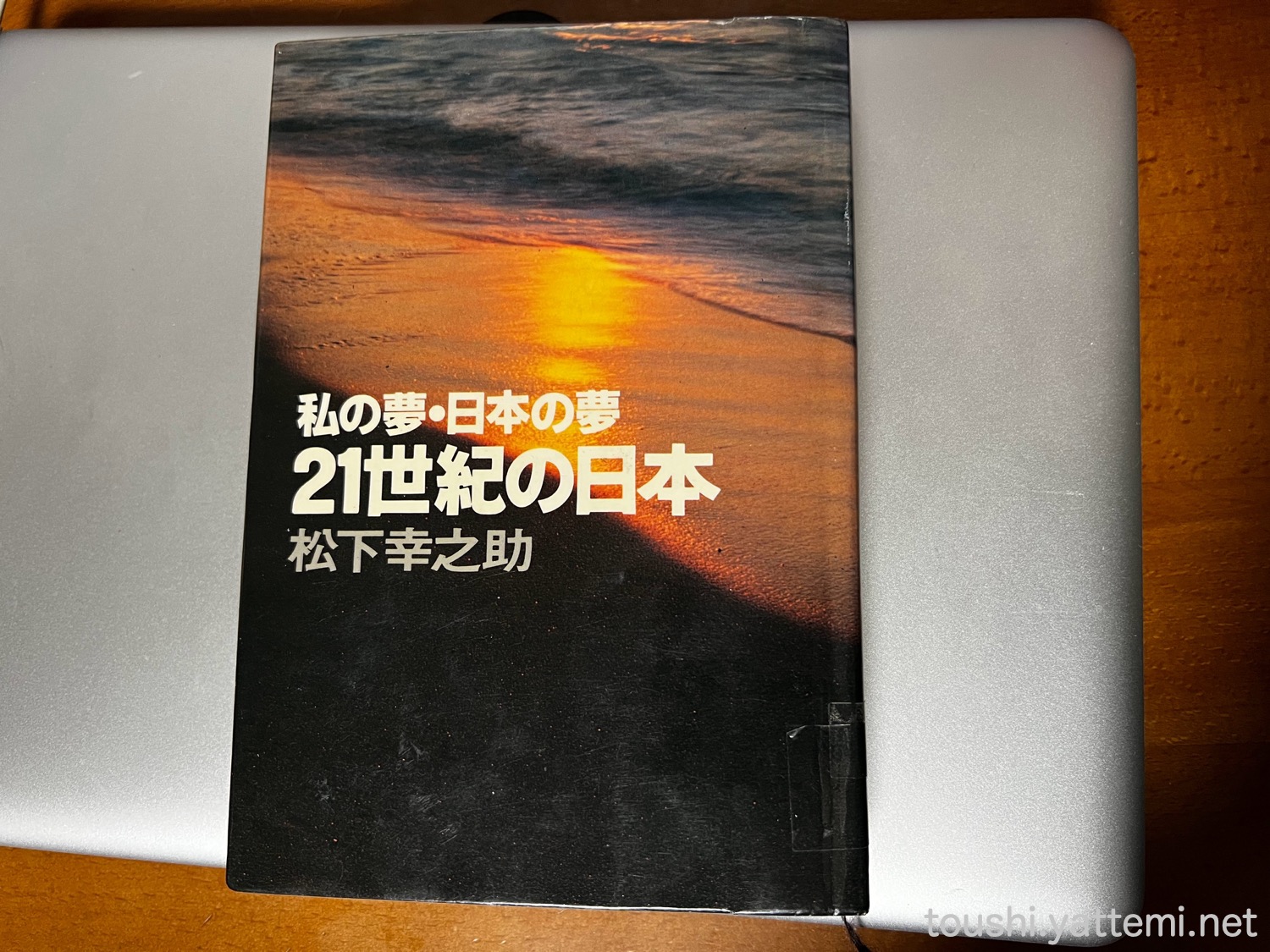今までに読んできた本の情報が
その人の「脳みそ」の引き出しに保存されて
その人の人格にも影響する。
・・・んじゃないかなぁ〜〜なんて思ってきたら、伝説のスピーチと言われているスティーブ・ジョブズの「スタンフォード大学の卒業式の演説(2005年)」で、「connecting the dots(点と点をつなげる)」という話を思い出すきっかけがありました。
「ハングリーであれ。愚か者であれ」 ジョブズ氏スピーチ全訳
米スタンフォード大卒業式(2005年6月)にてー日本経済新聞 2011年10月9日 12:00
読書も(仕事も生活も子育ても・・・)、読んでいるときはその本のことが中心になるのですが、なんとなくいろいろな本の内容(点)がつながっていき、線になり、面になり、立体化してきたことに、それなりのいい歳になって、やっと気づいたようです。
また「情報は金になる!」っていうのも同時に思い出し、実際にここ数年の生活を思い出してみると、情報を知っているか知らないかで金になっていることが多くなってきました。主に金銭的な投資ですが、自己投資も一緒だなぁ〜と。。
自分としてもせっかく読んだ本の内容をすぐに思い出せないことや忘れることがあるので、備忘録がてら読んできた本を一覧にしています。
(読んだ本は最初の部分に追加しているため、順番がバラバラしていてすいません。)
2025年に読んだ本
金持ち父さんの子供はみんな天才 親だからできるお金の教育
以前から気になっていたものの、手に取ることがなかった「金持ち父さんシリーズ」だったのですが、サブタイトルになっている【親だからできるお金の教育】という部分に惹かれて、読んでみました。
- 「私には買えない」ではなく「どうやったら買えるか?」
- 「仕事場では金持ちにならない。家で金持ちになる。」
- 「テーブルの向こう側」と「テーブルのあちら側」
- 学校システムは「大量生産のスケジュール」
- 「きみの家の負債と純資産の割合は?」
などなど、気になるワードや内容があり、楽しみながらサクッと読むことができる本でした。
オニールの成長株発掘法 - 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために
以前読んだ「1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術」で知ってから、図書館で予約していた「オニールの成長株発掘法 - 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために」が、あとちょっとで借りれそうなときにブックオフで売っているのを見つけたので買ってを読んでみました。
2001年発行の古いバージョンですが、「CAN-SLIM」法はちゃんと知ることが出来ました。
また「いつ売って利益を確定するか」ということも第10章にまとめられていて、ずっと気になっていた部分もしっかり書かれていました。
ただ、この本でも言われているのですが、やっぱり「損切り」が大事ですね。まだちゃんとできてないけど。。。
経済評論家の父から息子への手紙 お金と人生と幸せについて
18歳の息子に向けて書かれているのですが、子どもでも読めるような内容で、人生の大半を費やす仕事やお金の話が中心ですが、「モテ」や「酒の飲み方」など息子へ伝えておきたい面白いことも書かれていて、とても読みやすい本でした。
残念ながら著者の山崎さんは、2024年1月に亡くなられたのですが、父が息子に宛てた手紙をベースにしているので、率直に色々書かれているし、金融教育や投資を始めようとしている人にとっても、とても勉強になる著書だと感じ、手元に置いておきたい本の1冊になりました。
いま君に伝えたいお金の話
2018年に出版された本で、著者は投資家の村上世彰氏です。あの有名な「村上ファンド」の人ですね。最近のニュースを見ていると、娘さんとともにアクティビスト(物言う株主)として、ちょこちょこ見かけます。
そんな村上さんが、タイトルから分かるように子供向けに「お金」について書いていた本なので、試しに読んでみました。
日本で教育がうまくできていない「お金」の話を、子どもでもわかるように説明してくれているので、これから投資を始めようと思う人が読んでもわかりやすそうです。
ざっくりな内容は、「お金について」「お金の稼ぎ方」「お金の増やし方(借金も手の1つ)」「お金の使い方」という感じだったので、投資の入門書によくある感じでした。
プレゼント
2021年にずっと気になっていた『チーズはどこに消えた?』を読んでから、スペンサー・ジョンソンの著書『迷路の外には何がある? :「チーズはどこへ消えた?」その後の物語』『頂きはどこにある?』と3作読んできたのですが、Amazonにおすすめされて気になっていたので購入しちゃいました。
日本語で「プレゼント」と聞くと贈り物のイメージしかないのですが、英語だと「現在、いま」という意味があります。
なので「プレゼント」は「Present」(笑)
他の著書と同様に100ページ程度なのでサクッと読むことができるのでおすすめです。
第1子くんの音読教材にもしちゃいます。
失敗の本質 – 日本軍の組織論的研究
以前からいくつかの本で引用されていて、気になって購入したのですが、積読になっていた本をやっと読みました。
とは言うものの、この本を読み始めると、ほぼ半分までが第1章(過去の日本軍の戦争の失敗事例)なのでちょっと読みにくいのですが、2章3章はその事例を元にした現代の企業組織でも勉強になる「組織論」になっています。
ゆえ、第1章「失敗の事例研究」はノモンハン事件だけ参考に読んで、第2章「失敗の本質 ー 戦略・組織における日本軍の失敗の分析」、第3章「失敗の教訓 ー 日本軍の失敗の本質と今日的課題」をメインに読みました。
日本企業によくある論理的な内容ではなく「空気感や気分」が重要な会議や、少し前から話題の「Unlearning(アンラーニング:学習棄却)」、「創造的破壊」などのキーワードが、昭和59年(1984年)には言及されていることにちょっと驚きを感じつつ、やっぱり古典とまでは言わないと思いますが、昔から読まれ続けている本は学生のうちには読んでおいたほうが良さそうですね。
私の夢・日本の夢 21世紀の日本
松下幸之助が1967年雑誌に寄稿していた論考「株式の大衆化で新たな繁栄を」を見かけて、読んで調べていたら、日本証券業協会のサイトに辿り着き、さらに「松下幸之助.com」というサイトで見かけた「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」を読んでみました。
松下幸之助は、言わずと知れた「パナソニック(旧松下電器産業)グループ創業者」で「PHP研究所創設者」で、稲盛和夫(京セラ・第二電電(現・KDDI)創業者)と並び「経営の神様」と呼ばれている経営者ですね。
その松下幸之助が1977年に刊行した本が「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」で、刊行当時から43年後の21世紀(2010年)の日本のあるべき姿をストーリー仕立てで描いた著作になっていて、登場させる架空の政治家やリーダーの言葉を借りて自身の主張を述べています。
1970年代に考えられた2010年の話を、2025年に振り返ってみてみても、松下幸之助の理想状態になっていないのですが、想像できるものは実現すると思うので、まだ実現していない部分には注目しておいて、投資に活かしたいし、学びが多い!
思考の整理学
読み終わってから、Amazonで見てみたら「東大&京大&東北大&九州大(の生協)で1番読まれた本!」という紹介が書かれていて、1986年に初版が発行されていたのですが2024年2月に新版が発売されていました。
40年も読み継がれている本だったようですが、現代でもそのまま勉強になる本で、当時は「コンピューター」として人間と比較されているのですが、その部分は「AI」と読み替えることができるし、「思考」を通して「勉強」や「学習」、「書くこと」に関してもいろいろ学べるので、ぜひ手元に置いておいて子どもたちの音読用の本にしたい(笑)
読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術
著者の田中さんは、電通で24年間コピーライター・CMプランナーとして活動されていて、退職後「青年失業家」と自称しフリーランスで活動されているそうです。
コピーライターさんなので、表紙にあるようにすごくシンプルに「書くこと」を伝えてくれます。途中で、実際に使われた「履歴書」があったのですが、それをみると全体で言っていることがわかりやすい感じがしました!
また「物書きは「調べる」が9割9分5厘6毛」っていうのもグッとくる(笑)
人新世の「資本論」
以前からずっと気になっていたので、やっと購入して読んでみたのですが、2020年に発行されていた本なのでもっと早く読んでおけばよかったと感じる本でした。
コロナ禍になる前から株式投資や暗号資産投資を始めたので、投資に関する本をここ数年読んでいたのですが、「資本主義」に対する考え方がちょっと変わりました。
またタイトルにあるように、マルクスの「資本論」がメインにあるのですが、積読になっているアダム・スミスの「国富論」やトマ・ピケティの「21世紀の資本」についても触れられているので、個人的に読んでいる本が色々つながる古典のようなのでちょっと嬉しい。
2024年 以前に読んだ本